◆ブログ「青空リポート」・青陵SIに「相談機能」◆
―「地域の困りごと、気軽に聞かせて」―
―「日報生成AI研究所」と本格協働―
2025年10月18日
<「相談対応機能」いよいよスタート>
新潟青陵学園は15年後の2040年、「学園がソーシャルイノベーション(社会変革)のスクエア(広場)になる」ことを「2040将来ビジョン」として掲げています。その方向へ前進するための大きなステップとなる「青陵ソーシャルイノベーション推進機構(青陵SI)」を今年6月に発足させ、地域課題の解決を目指す協働事業を強化してきましたが、いよいよ今月中にさまざまな困りごとなどに対応する「相談機能」をスタートさせることにしました。
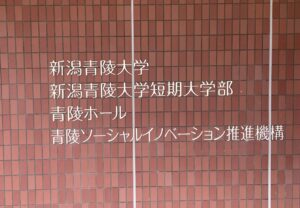 写真=青陵大学・短期大学部の玄関に、この夏「青陵ソーシャルイノベーション推進機構」の看板が加わりました
写真=青陵大学・短期大学部の玄関に、この夏「青陵ソーシャルイノベーション推進機構」の看板が加わりました
<教員100人の得意技を整理>
その準備として、本学園の大学院・大学・短期大学部に所属する100人ほどの教員の得意技・専門分野などを「資料集(シーズ集)」にまとめ、学園のホームページに掲載します。そして地域などからの「困りごと相談」などに簡便に対応できる態勢も整えていきます。
その時に頼りになる相談機器「青陵・答えるもん」の機能について、提携する「新潟日報生成AI研究所」と協議してきましたが、10月中にも相談機能を提供させていただくメドがつきました。本学園の青陵SIカウンターに置かれる「青陵・答えるもん」のほか、例えば地域のお集まりの際に「出張・困りごと相談」を実施する際は、最大30台の相談機器を使えるようにしていきます。「困りごと」などの内容について、キーをたたけば「青陵がその困りごとに対応できるか」を簡単に判断できるシステムで、対応できそうな場合は相談員に声を掛けていただきます。
本学園の創立125周年を祝う11月3日の記念式典には「相談機能スタート」の報告ができそうです。
<教員の得意技を分かりやすく紹介>
ご説明したように「この相談ごとに青陵学園が対応できるか」―を判定するには、教員たちの得意技や専門能力を分かりやすく示すデータ・資料集が必要でした。さまざまな協働事業のタネとなる資料集を私たちは「シーズ集」と呼んでいますが、その資料集を「7つの学園を経験してきた」佐久間春夫常務理事の指導で8月までにつくり上げました。市民向けに整理した「シーズ集」は、各教員からの資料を基に①私の研究キーワード②私はこんなことをやってきました③こんなことが提供できます。関心のある方、一緒にやってみませんか―の3項目にまとめてあります。
<広範囲な相談ごとに対応できます>
③の「こんなことが提供できます」をチェックしてみると、かなり広範囲な相談ごとに対応できそうです。ここでは大学看護学部を例に取り、提供できる事例の一部を紹介します
【「大学看護学部」の提供可能事例】
・「心臓マッサージ・AEDの指導講習」
・「中高生・保護者を対象にした思春期相談」
・「子育てと介護のダブルケアについて」
・「健康寿命延伸を阻む非感染性疾患の予防」 ・「薬物乱用の予防教育」
・「保健師仲間の語りの場・学び合いサロン」 ・「療養生活のお悩み相談会」
・「子どものスポーツにおけるケガ・痛みの処置法」
・「小中学生の看護師体験」 ・「家族看護の相談事例」
・「家族の引きこもり悩み相談」 ・「エイズ電話相談」
・「未来のケア・共創プラン」 ・「健康増進プログラムづくり」
・「特養における看護の問題」 ・「がん告知・意思決定支援」
・「生き甲斐や健康感の増進につながる『地域の茶の間』活動」
・「ストレッチによる生活習慣病の予防指導」
・「中小企業などの産業保健支援のための地域・職域連携の推進」
・「慢性期疾患と生活習慣の改善について」
・「病気になったら~どのように過ごし、どんな治療を受けたいか―〝人生会議〟のコーディネート」
・「診断のつかない手・指の痛み調査」―などなどです
【趣味・特技の分野も面白そうです】
・「信濃川の鮭の安定遡上環境は?」 ・「多くのトンボが羽化する環境は?」
・「ダンスイベントの開催」 ・「市内小中学校へのダンス指導」
・「タブレット端末の活用法」 ・「クラウドを活用した学びの継続的支援」―などが挙がっています
<地域に打って出る「パンフ」も作成中>
ここまで準備が進んできたので従来の「青陵SI紹介ミニパンフ」に加え、「青陵SIが本格稼働~気軽に困りごとをご相談ください」とアピールする新たなパンフづくりにも取り組んでいます。これも佐久間常務理事の考えなのですが、「データ集を学園のホームページに載せましたので、それを見てくださいというような姿勢ではなく、学園から地域に打って出ていく姿勢が大事」との考えの下、地域お届け用のパンフをつくることにしました。以下、予定している挨拶の文面を紹介します。
―みんなの力で地域課題を解決!―
「新潟青陵学園には大学院・大学・短期大学部に100人ほどの教員がいます。それぞれが専門分野を持っており、趣味・特技・余技も入れると、心身の健康や暮らしの改善、地域活性化など、かなり広範な分野で地域のお役に立てる陣容と思います。(ただ、これまではその情報を十分にお伝えできていませんでした。)
今回、青陵ソーシャルイノベーション推進機構(青陵SI)を本格稼働させるにあたり、青陵学園のホームページに教員力を分かりやすくお伝えするデータ・資料集「青陵力~こんなこと、一緒にやってみませんか」をアップしました。10月中には新潟日報生成AI研究所と組んだ相談機能「青陵・答えるもん」も稼働します。皆さんと一緒に地域課題の解決に取り組んでいきますので、よろしくお願いします」
ぜひ大勢の方から青陵SIの相談機能を活用いただきたい―そう願っています。
<既存事業に加え新規プロジェクトも>
次に相談機能以外の準備状況やこれまでの青陵SIの取り組みについてご報告します。
今年6月に「青陵SI」の看板を上げ、オフィスは青陵キャンパス1号館1階に仮設置し、主任相談員らを任命しました。継続事業として「青陵の森整備事業」や「ハマベリンク支援事業(海岸クリーン作戦など)」、「月見草復活プロジェクト」などを実施しています。また、関連事業として「スポごみ日本選手権」では青陵アルムナイ(同窓会)チーム「スマイルストーリー」が2連覇を達成し、「スポごみW杯」の日本代表にも2回連続で選ばれることが決定しました
新規事業としては青陵高校の探究の時間を活用して開始した「未利用魚活用プロジェクト」があります。こちらの主役は「エソ」です。「出汁はうまいが小骨が多く、新潟ではほとんど利用されてこなかったエソ」を新たな食材とする取り組みです。日本財団が主催し全国で展開する大会にも参加。60余校の中から「未利用魚活用全国大会」に出場する9校に選ばれました。11月に開催される全国大会の結果が楽しみです。
<「ENGAWAプロジェクト」も始動>

 写真(左)=青陵学園が新潟市と組んで有効活用しようとしている空き店舗。従来はゴミがあふれている状況でした (右)=青陵の学生らが9月末から大掃除に乗り出しました
写真(左)=青陵学園が新潟市と組んで有効活用しようとしている空き店舗。従来はゴミがあふれている状況でした (右)=青陵の学生らが9月末から大掃除に乗り出しました


写真(左)=学生は先生方の指導の下、交代でゴミ片づけをしてくれています (右)ゴミの量が半端ではないので軽トラックで焼却場に何度も運び出します
また、まちなかの空き店舗を活用して学生の活動拠点をつくり、地域住民と交流しながら地域の活性化案の提案や実践を進めようとする「下町ENGAWAプロジェクト」が新潟市との協働事業に採択されました。これは「ふるさと納税」と「クラウドファンディング」を組み合わせたシステムで、中央区下本町にある空き店舗を整備し、学生たちが住民と協働事業を展開する活動拠点とするプロジェクトです。クラウドファンディングの目標金額は233万円。ふるさと納税を活用することで「低額寄付で大きな効果」が得られます。
 写真=空き店舗は「フレッシュ本町」の一角にあります
写真=空き店舗は「フレッシュ本町」の一角にあります
例えば「ENGAWAプロジェクト」にふるさと納税で2万円のご寄付をいただくと、翌年、1万8千円分は税金が還付されますので「実質2千円の寄付」でプロジェクトにご協力いただけます。集まった資金は空き店舗の清掃・整備費や備品購入費などに充てることになります。10月末が締め切りです。「ふるさと納税で応援」のQRコードを添付しましたので、是非チェックいただいた上でご協力をお願いします。


写真(左)=学生が空き店舗の清掃に奮闘してくれています (右)=お陰で10月半ばにかなり綺麗になりました。もう一息です


写真(左)=新潟市が作成した「ENGAWAプロジェクト」のチラシ (右)=クラウドファンディングのQRコードです
<下町を先行事例に地域との協働強化>
青陵SIでは今回の下町を先行事例として、地域との協働を強化していきます。まだアイデア段階ですが「モンゴルとの交流の加速」もその一つです。いま、青陵学園にはモンゴルからの留学生が高校に2人、大学に1人来ています。いずれも本学園と連携協定を結んでいるモンゴル・エルデミーンエフレル学校からの留学生で、今後さらにモンゴルからの留学生誘致に力を入れていきます。その際、特に未成年の高校生には寄宿舎のような施設が必要です。下町には空き家・空き店舗が数多くあるので、地域との関係を強化しつつ、下町にモンゴル人留学生の寄宿舎ができないか、下町の方と意見交換しています。モンゴルからの留学生が日本の地域に溶け込み、地域の方から励まされながら青陵学園に通えるようになれば最高の国際交流になる可能性があると考えています。そうなれば青陵の県外からの学生たちも下町に寄宿する可能性が高くなります。

 写真(左)=10月3日には同郷の縁で伊勢ヶ浜親方(元横綱・照ノ富士)が青陵高校のモンゴル人留学生を激励にきてくれました (右)=留学生は色紙にサインをしてもらい感激していました
写真(左)=10月3日には同郷の縁で伊勢ヶ浜親方(元横綱・照ノ富士)が青陵高校のモンゴル人留学生を激励にきてくれました (右)=留学生は色紙にサインをしてもらい感激していました
「湊町にいがた発祥の地」である下町ですが、長く人口流出に苦しみ、高齢化率は新潟市で一番高いエリアになっています。その下町に学生・生徒たちの拠点ができ、そこから発展して「留学生・学生の住まいの拠点」ができれば、下町が元気になり活性化していくのでは―と夢を広げています。
青陵SIではそんな先行事例をつくりながら、地域との連携・協働を進めていきます。協働事業を学生・生徒たちの育ちにつなげ、その活動が地域を元気にするよう展開していきます。「青陵SI」をご活用ください。
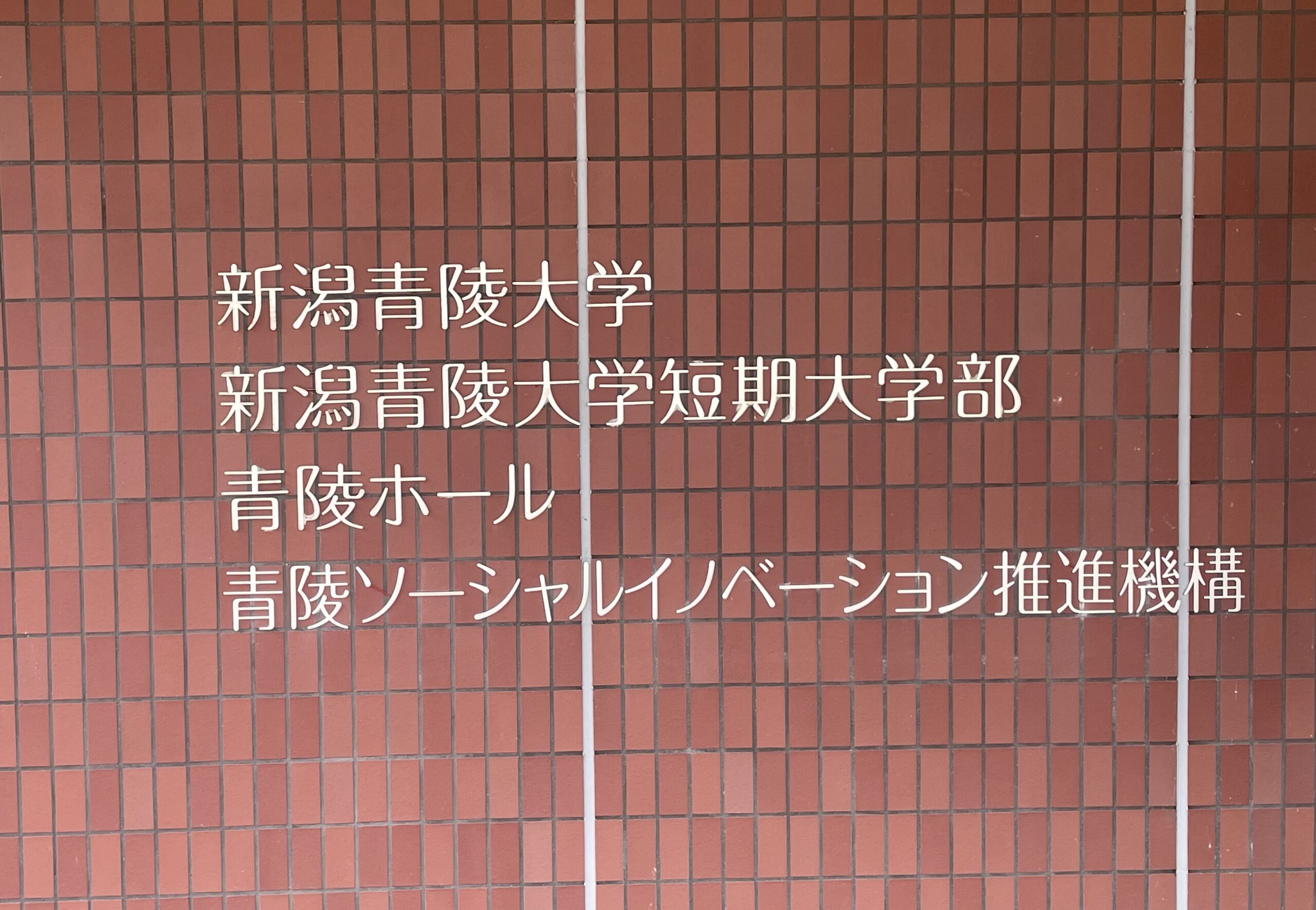

コメント