◆ブログ「青空リポート」・青陵で看護学術集会◆
2025年9月2日
―アディクション(依存症)について学ぶ―
―ご当地講演は「新潟清酒」をテーマに―
<暮らしとアディクション>
8月30、31の両日、新潟青陵大学で「日本アディクション看護学会・第23回学術集会」が開かれ、全国から約200人の研究者・関係者が集まりました。今回のメインテーマは「暮らしとアディクション」。アディクション問題を抱える人々が地域で安心して暮らせる社会を実現するためにはどうすれば良いのか―多角的な視点から議論を深めることが今回の学術集会の狙いです。
 写真=本学園の「青陵ホール」をメイン会場に開かれた「第23回アディクション看護学会学術集会」
写真=本学園の「青陵ホール」をメイン会場に開かれた「第23回アディクション看護学会学術集会」
今回の学術集会長を務めた青陵大学の田中瞳准教授は、「依存の対象となりうるものは、私たちの身の回りに溢れています。それらの多くは、本来、暮らしを豊かにし、楽しみや喜びをもたらし、文化的な営みを育むものであり、決してそれ自体が〝悪〟であるわけではありません」と言います。
<暮らしに潜む依存の要因にメス>
確かにアルコールをはじめ、暮らしに適度な彩を添えてくれる嗜好品や遊び事は大事な文化に違いありません。今やインターネットやスマホも暮らしには欠かせません。しかし、適切な距離が維持できなくなると、その関係性は歪み、「依存」という問題が発生します。
そういう時も依存する対象(アルコールやギャンブル、インターネット、人間関係)を単に排除するべき〝悪〟と捉えるのではなく、暮らしに潜む依存の要因を深く掘り下げ、「適切な距離」を回復し、安定した暮らしを送るための看護のあり方を考え、医療の枠を超えた社会全体のネットワークについて考えるのが今回の学術集会の特徴のようです。
<県酒造組合やJRAも後援>
「依存の対象を単に排除するものと捉えるのではなく、適切な距離の取り方を社会全体で考えていく」―学術集会のこの基本的スタンスを聞いて、アルコールや勝負事と長く付き合ってきた私は大いに共感しました。「依存症と向かい合うには社会の包括的な支援が必要で、単に病気を治すのではなく、その人の人生全体を支えることと捉え直す必要がある」との学術集会の基調にも頷けるものがあります。また、アディクション学会の後援をお願いした県酒造組合やJRAの反応を見ても、この考え方は社会に受け入れられるし、これから深掘りしていく方向と思います。
今回の学術集会は、県や新潟市、県看護協会、県社会福祉協議会、新潟市医師会などだけでなく、法務省、厚労省からも後援をいただくことになりました。それも「社会全体でアディクションを考えていこう」との考え方に賛同の輪が広がっている証と受け止めたいと思います。
<「適切な距離を求めて」>


写真=学術集会長としての冒頭挨拶に続き、「暮らしとアディクション」について講演する田中瞳・青陵大学看護学部准教授
30日の学術集会の冒頭、「学術集会長講演」で田中准教授は「暮らしとアディクション~人やモノとの適切な距離を求めて~」と題してお話しされ、今回の学術集会の問題意識を次のように述べました。
―依存対象となりうるモノや行為は、単なる快楽の追求に留まらず、社会の基盤となる文化や産業と密接にかかわっています。アルコールを例にとると酒造り・酒販売・飲食店経営は多くの人を支える重要な仕事であり、産業です。特に日本酒文化が根付く当地・新潟県においては、日本酒は単なる嗜好品ではなく、地域の歴史や文化、ひいては人々の誇りそのものなのです。
本学術集会では、依存症を特定の物質や行為の問題に矮小化するのではなく、人々の暮らし・文化・産業との関連を踏まえ、多角的な視点から捉えていきたいと思います。依存症を抱える人々が、暮らしの中で依存対象と「適切な距離」を回復し、安定した生活を送るための看護のあり方、さらには医療の枠を超えた社会全体のネットワーク構築について、皆さんと議論を発展させる機会としていきたいー
<「依存症を再定義する」>


写真=「特別講演」で講演する佐久間寛之・さいがた医療センター院長
田中講演に続き、学術集会の基調を成す「特別講演」では「もう一度依存症を再定義する~レジリエンスと心的外傷後成長、そして楽観的であることの価値~」と題して佐久間寛之・さいがた医療センター院長がお話されました。その内容も「社会から依存症を排除しない」との方向を明確に示すものでした。
「依存症に悩む人間から、その対象物を取り上げたり、無理やりやめさせようとしたりする〝直面化〟や〝対決技法〟は無効であるばかりか、心的苦痛を高め、より自己破壊的な依存行動への増悪因子となり得る。そうではなく、非対決的で共感的な〝治療同盟〟の構築が必要である」と説く佐久間院長のお話は大変に含蓄の深いものでした。
佐久間院長は「依存症は暮らしや生活の中で発症し、その人の暮らしを損ない、家族や周囲の人を巻き込んでいく疾患です。しかし、本人、家族、そして支援者もレジリエンス(こころのしなやかさ)と希望を持ち、社会から依存症を排除しない姿勢が望まれる」との方向性を語られました。
<新潟清酒の魅力を語る>
2日目の31日には「ご当地講演」として、新潟清酒づくりのリーダー役のお2人が登壇しました。一人は新潟大学教授で日本酒学副センター長を務める平田大さんで「世界初の日本酒学(Sakeology)について」講演されました。もう一人は(株)麒麟山酒造社長の齋藤俊太郎さんで、こちらは「新潟清酒の魅力」について語ってくれました。お二人の講演も今回の学術集会の基調に添ったもので、日本にとって、新潟にとって「酒造り文化」がいかに大事であり、人々の誇りにつながるものであるかを示してくれました。このセッションの座長は本学短期大学部の村山和恵准教授が務めてくれました。
 写真=座長を務めた村山和恵・短期大学部准教授
写真=座長を務めた村山和恵・短期大学部准教授
<多彩なセミナーや展示も>
今回の学術集会ではこのほかにもシンポジウムや教育講演・セミナー、公募型交流集会、企業との共催セミナーなどが開かれ、ポスター展示・企業展示なども行われました。
全国的な学術集会を青陵大学が中心となって開催したことで、「青陵の力」を多くの方にご認識いただけたのではないかと感じています。学術集会長を務めた田中准教授、猪浦智史・実行委員長をはじめ本学の企画委員の皆さん、運営に当たっていただいた皆さん、大変ありがとうございました。
また、県内でご協力をいただいた長岡崇徳大・新潟薬科大・新潟大・新潟県立大、医療・福祉関係者らの皆さま、並びに共催・協賛・ご賛同をいただいた企業・法人・団体などの皆さまにも深く感謝申し上げます。ありがとうございました。次回は来年8月末に湘南医療大学で開催されます。

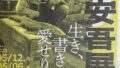

コメント